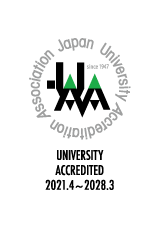新潟リハビリテーション大学
学長 山村 千絵
新潟リハビリテーション大学(以下、本学)は、平成19年4月に大学院だけの新潟リハビリテーション大学院大学として開学したのち、平成22年4月に学部を増設して現在の姿になりました。新潟県北地域唯一の保健医療系大学であり、教育・研究成果を学生と教職員が一体となって地域に還元し、地域住民の保健・医療・福祉環境の向上にも寄与しています。
とりわけ、本学の位置する村上市とは、包括連携協定のもと強い相互協力体制を構築し、専門分野に限らず、学生・教職員ともに幅広い活動を展開しています。たとえば、地域のお祭りや国際トライアスロン大会等をフィールドとしたボランティア活動を実施したり、子供から高齢者までを対象とした、福祉活動の体験、健康講座、生涯教育を提供したりしています。近年は、現代社会に必須な防災教育にも重点を置き、学生に「生き抜く力」を涵養しています。災害時の避難所における学生の活動は、地域住民からも大きな信頼と評価を得ています。
建学の精神として「人の心の杖であれ」を掲げ、医療学部における養成する人材像は次の通りとしています(令和7年度からリニューアルしました)。
(1)崇高な倫理観と医療従事者としての使命感を常に有し、主体的に行動できる人材の育成
(2)豊かな人間性と広い見識・教養・技術を有し、地域社会に貢献できる人材の育成
(3)多様な者と協働し、専門性を発揮しながら国際社会に貢献できる人材の育成
さて、近年、少子化による若年人口の減少をはじめとした社会状況の変化が急速に進んでいます。そして、そのような変化に対応できる大学の大きな組織改革が求められています。社会の荒波に立ち向かっていくために、本学は、令和7年度より、さまざまな改革を行っていきます。
その改革の先陣として、「人の心の杖であれ ~ひとり一人が主役になれる多様で個性的な学びの支援~」事業を実施します。多様な背景を持つ学生ひとり一人が主役になれる、学修者本位で個性的な学びを支援し、養成する人材像(上述)のように、地域社会・国際社会に貢献できる人材を育成していきます。
なお、本事業は、文部科学省の令和6年度「少子化時代を支える新たな私立大学等の経営改革支援」事業の「メニュー1 少子化時代をキラリと光る教育力で乗り越える、私立大学等戦略的経営改革支援」に申請し選定されました。本事業の趣旨は、「少子化を乗り越えるレジリエントな私立大学等への構造転換を図るため、日本の未来を支える人材育成を担い、付加価値を創出する新たな私立大学等のあり方を提起し、将来を見据えたチャレンジや経営判断を自ら行う経営改革の実現を図るための支援を行うこと(文部科学省ホームページより)」であり、これにより、今後5年間、国から継続的に支援していただけることになりました。
多様な学生を受け入れるにあたって、入学前までの学びや経験だけからでは将来の職業を決められなかったり、入学後に別の分野に興味が湧いたりする場合も多々あることを想定し、入学後も柔軟に進路を変更・選択できるよう、令和7年度より転専攻制度をバージョンアップしました(本学は10年前から転専攻制度を設けていましたが、カリキュラム上、制限がかかることもありました)。1~2年次は将来の専門性を見極める時期とするため共通の基礎を固めるべく、専攻共通の科目を多く用意しました。各専攻の教員がオムニバスで1つの科目を受け持ったり、転専攻後の専攻必修未履修科目対応のために、授業や試験日程等の工夫も行ったりします。これらについては、本パンフレットにおいても、「特色ある教育課程」として、カリキュラムツリーモデルを用いて説明しています。
最後になりましたが、本学は知の拠点として、教育、研究、社会貢献活動等を通じて、社会に山積する様々な課題解決に貢献しています。その原動力となっているのは、熱意があり意欲的に日々努力を続けている学生たちや教職員の皆さんです。取り組まなければいけないことは数多くありますが、皆で心を一にして、未来に向かって進んでいます。もちろん、学生たちの夢や希望が叶うように、卒後も含めて、教職員一同でしっかりとサポートしていきます。本学で一緒に学び、成長しましょう。