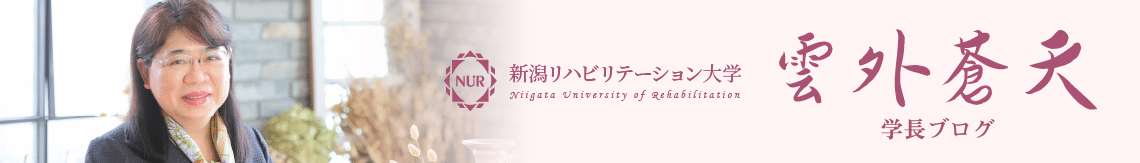3月24日(木)、東京ガーデンパレスで開催された公益社団法人私学経営研究会主催の学校法人のガバナンス改革セミナーに参加してきました。会には、全国各地から私立大学関係者が90名ほど集まり、2人の講師の話に耳を傾けたのち、講師と参加者が意見交換を行いました。
1つ目の講演は、追手門学院大学学長の坂井東洋男氏による「追手門学院大学ガバナンス改革の軌跡」でした。前任校である京都産業大学学長時代の裏話から始まり、追手門学院大学学長に着任した後に進められたガバナンス改革について、時折ユーモアを交えながら、テンポの良い話が続きました。着任当初の教授会は、6~8時間と長時間にわたる会議で、しかも、いくら議論しても結論が出ずに紛糾して終わったり、あるいは、結論が出ても実行されないまま時が流れていったりすることが多かったそう…それが、今では、教授会を学長の諮問機関と位置づけたことで、1時間程度で終わるようになり、余った時間を有効活用できるようになったとのこと。本学の教授会も、最近は議題が多いこともあり、3時間以上続いてしまうことが多いのですが、短い時間で効率よく切り上げたいものです。
2つ目の講演は、尚絅学院大学学長の合田隆史氏による「地方中・小私学の学長の立場から見えること」で、タイトルが、まさしく本学に当てはまることであり、興味深く拝聴させていただきました。マネジメント改革が進まない「尚絅学院大学のあるある」として、次のような事項を掲げられていましたが、妙にうなずけるものでした。・手放すこと(確実に失うこと)への恐怖・得るものの不確実性への恐怖・未経験の仕事に取り組むことへの負担感・問題点の指摘のレベルでは極めて優れている一方、ではどうすれば問題を克服できるかのレベルになると思考が完全に停止する・細分化された「役割」への忠誠心と誇り・自分の「役割」を超えた課題への無関心・目先のことに極めて忠実なあまり、それだけで時間切れになり、先のことは考えない習慣・飲み会の時はいいアイディアがたくさん出て盛り上がるが、翌日には「とりあえず」の世界に戻っている。
本法人では3月23日(水)に、今年度最後の理事会が開催され、新年度の事業計画をはじめ多くの重要事項が審議・決議されました。大学の事業計画にも多くの改革を盛り込みましたが、今日のセミナーも参考に、より効率的な改革の進め方を探っていきたいと思います。