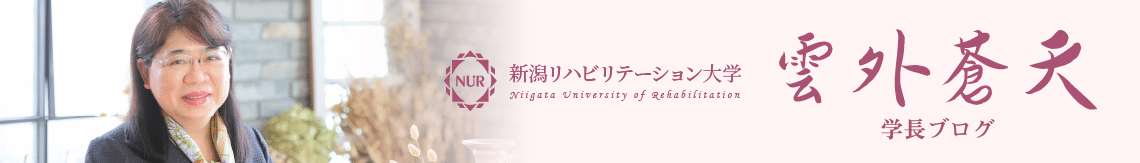今日は、今年度の臨床評価実習指導者会議がありました。この会議は、11月から学外の病院に臨床評価実習に出ていく3年生の受け入れ先となる病院の指導者に対し、本学の教員が、本学の教育方針や依頼する実習内容の概要を説明するとともに、両者間で実習の到達目標・進め方等を協議・確認する目的で、毎年開催しているものです。また、実習に向かう学生が、実習先の指導者と直接面談を行う場面もあり、実習前の緊張を少しでも和らげてもらいたいという意図も含んでいます。
会議は専攻別に会場を変えて行われました。私は言語聴覚学専攻の会場に参加させてもらいました。写真は、言語聴覚学専攻の3年生が、指導者を前にひとりずつ自己紹介をし、実習に臨む意気込みや意欲を伝えているところです。私自身はリハビリ関連職ではないため、このような臨床実習の制度は、学生時代に経験していません。私の学生時代の歯学部での臨床実習は、5年生の後期から6年生にかけて、大学の附属病院で行われたため、学外の病院へひとりで出向いて、実習を受けるというドキドキ感はそれほど感じることなく過ぎていきました。しかし、学外の勝手がわからない病院に配置され、いつもの友達が周りにいない中、ひとりで実習に臨むことは、かなりのプレッシャーだと思います。その分、やり遂げた後の達成感、自信は、はかりしれないほど大きなものがあるでしょう。臨床実習中の学生さんは、いろいろとストレスをかかえることもあると思いますので、保護者の皆さまには、できる範囲で暖かいサポートをお願いできればと思います。臨床実習が円滑に進み、充実したものとなるよう、願っています。
昨日は、来年度から立ち上がるリハビリテーション心理学専攻のカリキュラムに組み込まれている産業カウンセラー受験資格を得るための講義や実習の打ち合わせを、日本産業カウンセラー協会の担当者の方々と、本学側の関係者とで行わせていただきました。大学のカリキュラムの中で、産業カウンセラー養成科目を取り入れているのは、現在、国内では4大学のみ、本学が5番目になるとのことでした。本学が開講予定の「産業カウンセラー心理面接演習」の科目では、全面的に協会のサポートをいただくことになります。演習では、就職面接にも役立つ傾聴技法などを学んでいきます。