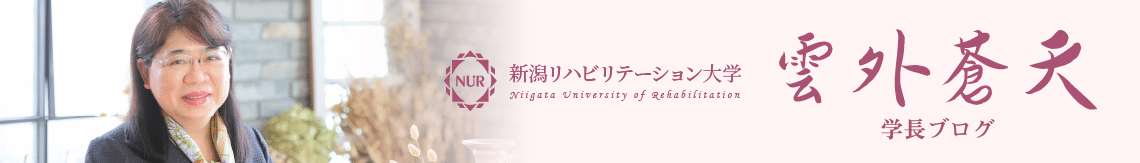本学では地域貢献活動の一環として、平成23年度より、地域の高齢者の方々を対象とした「転倒予防教室(転ばぬ筋力アップ教室)」を春・秋ともに10クールずつ開催しています。本教室は、本学会場のみならず、隣接する関川村にも出向いて実施しています。理学療法学専攻の教員が中心となって実施していますが、教室立ち上げ初期のころから、学生たちにもサポートに入ってもらっています。
また、コロナ禍前までは、「食べる力をつける教室」も開催していて、さまざまなトレーニングを実施していましたが、コロナ禍以降は、同教室自体の開催は中止して、「転倒予防教室」の1コマを借りて、「食べる・飲み込む」に関する啓発活動やトレーニングの紹介等を年2回、私自身が行っています。
11/17の回では、誤嚥性肺炎の予防等に関して、指導をさせていただきました。あいにくの悪天候・冬空にもかかわらず、参加していただいた方々には、熱心に受講していただきました。スライド・プリントや解剖模型を用いながら、「むせない誤嚥」もあるので注意が必要なことについても、お伝えしました。質問がたくさん出て、皆さんの関心の高さが伺われました。
ところで、いつもの「転倒予防教室」は上述したように、教員主体で行い、学生はサポート役を担っていますが、私が担当した前週の11/10の回は、企画から運営まですべてを学生が行い、堅苦しい内容ではなく、楽しみながら効果のあるレクリエーションを行う回でありました。手作りの道具を使ったボーリングや輪投げを取り入れて、会場は大きな笑い声に包まれていました。この回は、地元紙にも取材に来ていただき、先般の全国学生調査の結果と連動させて報道される予定となっています。
大学での学生の学びは授業のみではありません。大学をベースとした、地域での活動(授業外のアクティブラーニング、様々な背景を持つ様々な年代の人たちとの出会いや交流等も含め)すべてが学びの機会であり、我々教職員は、学生たちに、多感な若いうちに、できるだけ多くの授業外の体験の場も設けてあげる、ということも重要な役割と思っています。
授業での地域ボランティア活動は入学後の早い時期に行わせる意味で1年生の前期(9月末まで)に行っています。今年度の授業内プログラムはすでにすべて終了しましたが、授業外でもさまざまな体験ができるように工夫をしています。このような、より現場に近い体験をすることは学生を大きく成長させます。授業という型にはまった枠の中での活動のみならず、自分が興味を持った地域活動に手を挙げて参加していく、ということは、とても重要と思います。
予測困難な時代となり、従来のような、教室内での授業のみではこれからの時代を生き抜いていくために必要な力を十分に養えないでしょう。今後も、学生たちを外に出して、地域でも育てていただけるよう、さまざまな体験をさせていきます。
中央教育審議会より2018年11月に、(急速に少子化が進む)「2040年に向けた高等教育のグランドデザイン答申」がだされています。答申では、学修者が「何を学び,身に付けることができるのか」を明確にし,学修の成果を学修者(学生)が実感できる教育を行うこと(学修者本位の教育)。このための多様で柔軟な教育研究体制が準備され,このような教育が行われていることを確認できる質の保証の在り方へ転換されていくことが提唱されています。
先日、本ブログでも紹介した「全国学生調査」は、まさしく学修者本位の教育が展開されているかを確認する調査(教員目線ではなく学生目線)であり、大学での(授業だけではない)多様な学びの成果を測定し、その結果が反映されたものと考えます。